みなさん、双子が産まれたらどうするんだって聞いてんだよ。
名前だよ。双子の名前、どうすればいいわけ。たとえば一方に葵(あおい)、他方に奏(かなで)と名づけたとして、そんなおかしいことってないですよね? 名前には必然性が要る。健やかに育ってほしいとか周りを笑顔にしてほしいとか、そういう願いを込める。あるいは、寺の僧侶につけてもらったり画数を占ったりと、縁起的なポテンシャルを期待する。なんにせよ、建前やこじつけであっても何かしらの必然性のもとに名づけるというのが、現代の日本文化における命名の倫理だ(そうなんですか?)。
じゃあ双子、とりわけ一卵性双生児が産まれそうになったらどうするのって話。一緒じゃん。助産師さんに「なんで葵(あおい)は奏(かなで)じゃなくて、奏(かなで)は葵(あおい)じゃないんですか?」と訊かれたら、答えられるか。奏ちゃんが葵ちゃんよりピアノが上手かったりすれば話は早いけれど、助産師さんと話してる時点では、そういうのないじゃん。しばらくはほぼ同一人物だ。胎児の段階では、ピアノを弾かせても似たり寄ったりの結果になるだろうし、ビジュアルも似たり寄ったりだ。服着てないし。あまりに可換だ。もし甲に「まっすぐな子に育ってほしい」と願って「まお」と名づけようものなら、ただちに乙も「まお」にしてまっすぐな子に育ってもらおうと願わないと、倫理的にエラーになるんじゃないか。「まお」以外の名前にしたら、まるでこの子にはまっすぐな子に育ってほしいと思ってないみたいになってしまう。逆もまた然りで、乙につけた名前の必然性を、甲には担わせないことの説明がつかない。数学の証明問題だったら便宜的にX,Yと名づけて最後に「対称性よりXとYが逆の場合も成り立つ。」と書いて証明終了するところだけど、役所でそんな便宜は効かせてもらえない。甲はこの名前、乙はこの名前と言いきれる根拠が届出の時点で無ければならないのだ。どうにかして、二人に異なる名をつける口実を見つけないと……。「甲と乙」くらいドライな目線で二人を見なければいけない。しかし、見比べてもせいぜいグラム単位の大きさの違いか、先に産まれるか後に産まれるかの順序……その程度の要素しか見つからないのである……。
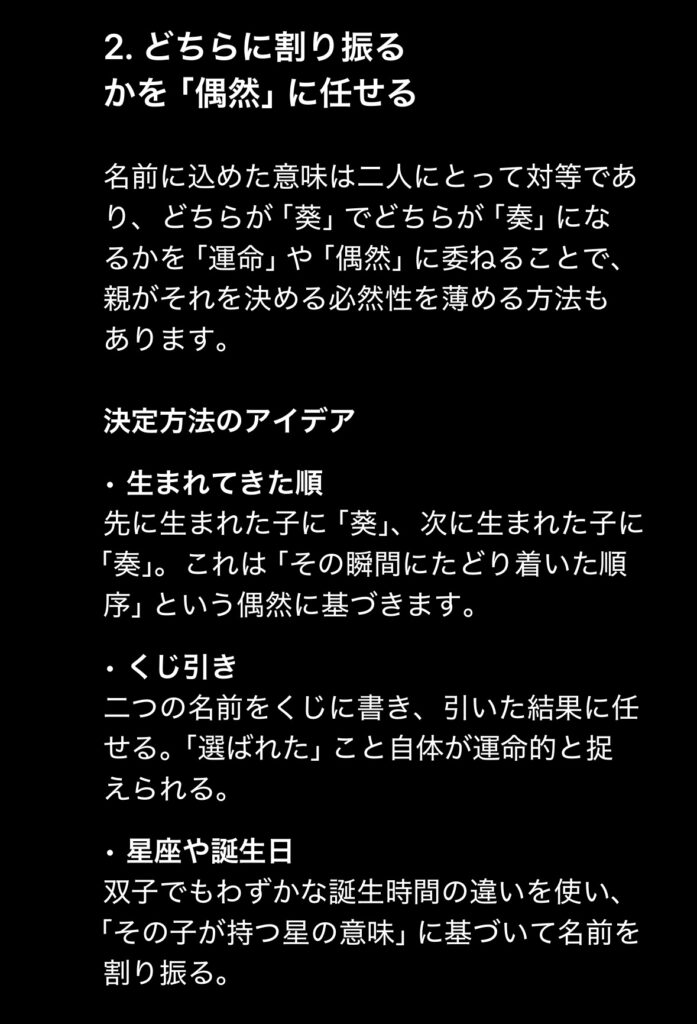
ChatGPTに仰いだ意見。「偶然に任せる」は僕もベターな方法だと思う。偶然性も、名づけの倫理においては十分に必然性の材料となる。まず産前に、異なる二つの名前を用意しておく。分娩までは、どっちがどっちとは決めないでおく。母体から取り上げたあと、二人の赤子を中華テーブルの上に置いて、回すのだ。二つの名前に東西を割り当てておいてルーレットの要領で結果を得れば、それぞれの子に「ふさわしい名前」を与えることができる。回したらどっちがどっちだったか医者も助産師も親も分からなくなりそうだけど、それで良い。限りなくフラットな立場から始め、名前を与えると同時にそれぞれのユニークな人生を出発させる。
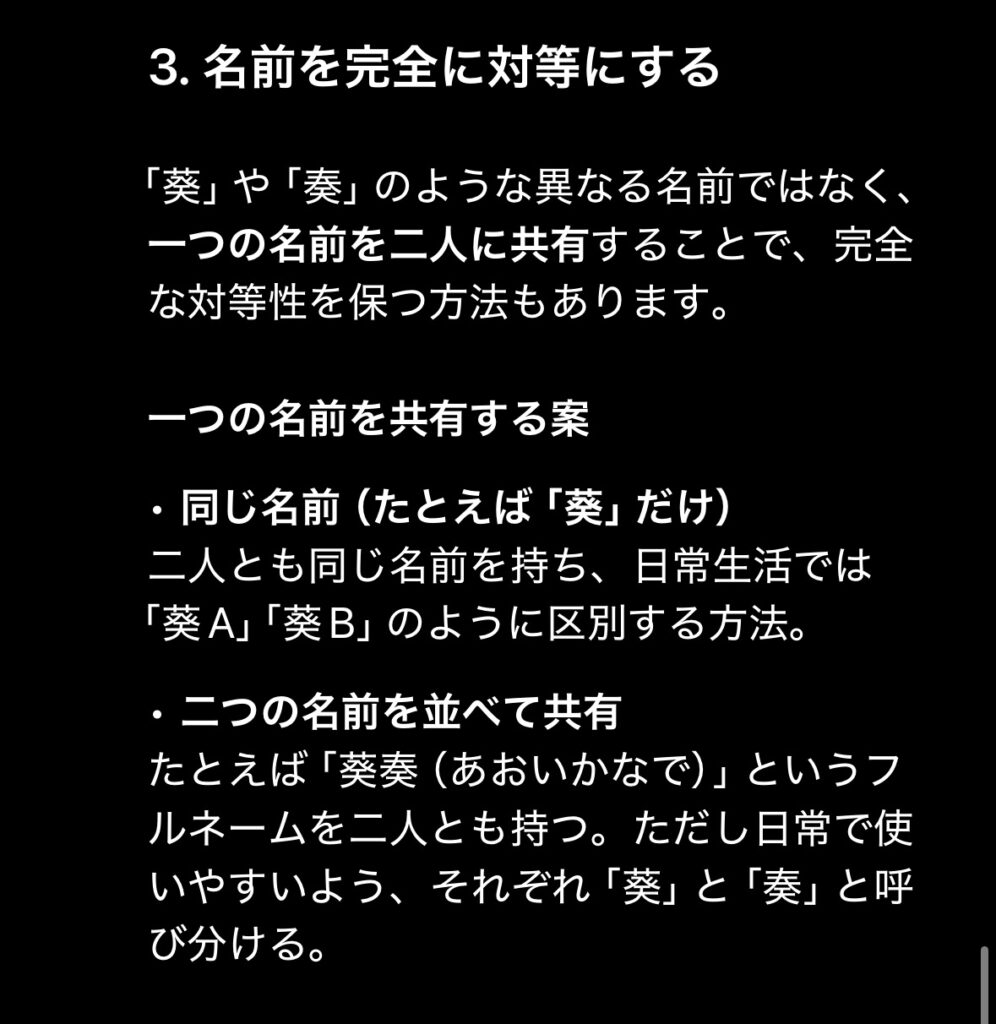
「名前を同じにする」という提案も受けた。名前の本質に肉薄している。日本の法律的にいけるのかは分からないけど、海外の文化圏なら同じ名前にするみたいな風習は実際ありそう。二人とも「葵奏(あおいかなで)」にしておけば、どちらを葵、どちらを奏と呼ぶかを時間をかけて決められるので、より精度の高い必然性を与えられる。東大の進振り制度くらい合理的だ。
2人とも酒やギャンブルを愛す。
ダイタク – Wikipedia
朝9時に起きた。13時間眠っていた。昨日眠いのをこらえてプールで泳いだからか。顎の痛みがあるが、これは昨日歯医者で新しいアライナーを装着されたからか。カーテンを開けて太陽と街の関係を確認した。
昨日はいい日だったな。何もなくて。
気づいたら11時になった。何もできない。今日は午後に学校の授業があるのと、20時以降にゲーム関係の人と会って何かの相談をする(何の相談なのか知らない)予定があって、授業後から相談までの夕方のすきま時間をどこでどう過ごすべきかみたいなことを考えていたら、どうしようもない気がして鬱っぽくなってしまった。
11時40分に家を出るなら、今から歯を磨いてシャワーを浴びて髭を剃って爪を切ったらもう出る時間になるのか。この文を書いてる間にもう11時11分。
午後どう過ごすかは、電車内で考えるか。動こう。お、14分になった。まだ動いていない。15分になった。すごいな。16。立ち上がる。
爪切りを終わらせたら、12時20分になっていた。全然間に合ってない。大学に出席するのは諦めた。今日は鉱物と標本観察の授業だと予告されていた。行きたかった。今から行けば遅刻でも受けられるけど、でもなんか無理そうだったので早めに諦めた。一度キャッシュをクリアして動きかたを決めよう。
僕は高木正勝の音楽を聴きながら、4駅離れた文房具屋に、歩いて行くことにした。散歩と日光浴を兼ねて。それからジョナサンでご飯食べて、授業に出られなかったぶん、家でゲーム開発しよう。
文房具屋でノートとペンとハサミを買った。

ハサミ。11月8日に買う予定だったハサミをついに買えた。このようにリマインダーに登録することで、タスクを忘れずに管理することができる。
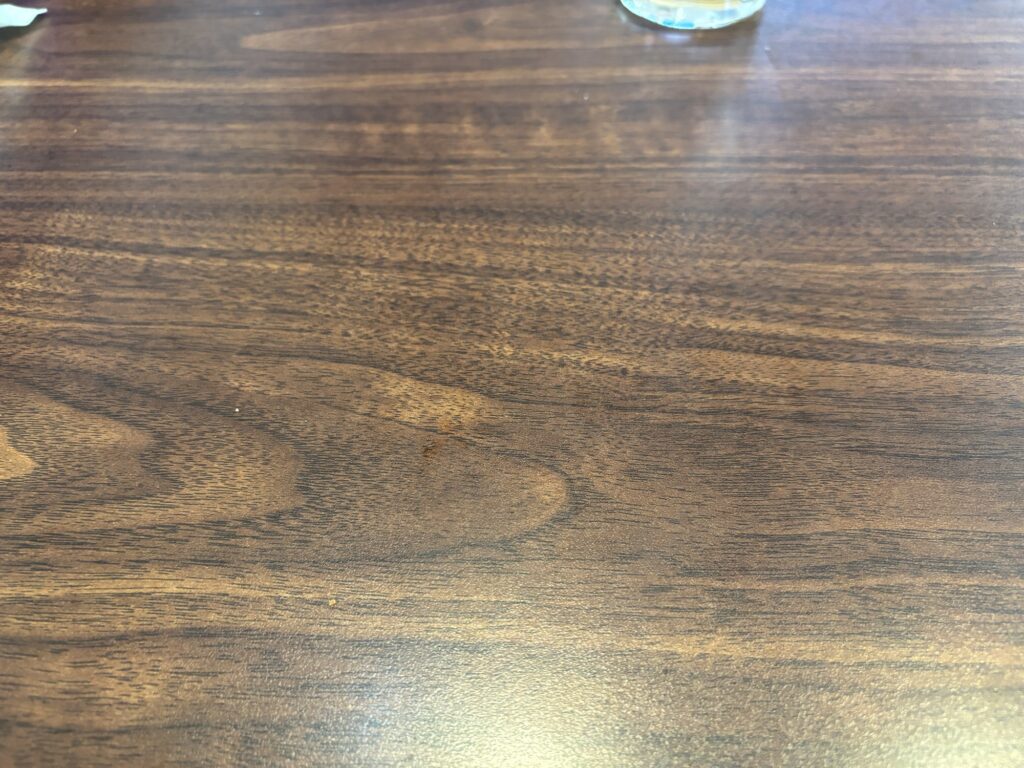
ジョナサンでお昼ご飯を食べた。写真を撮ろうと思い至ったときには皿が回収されていた。
Discordで友達から「進捗どうですか?」と連絡が来た。そういえば、11月にクラスメイト数人と一緒にゲームを作ろうと約束していたことを思い出した。僕が企画担当だったが、放ったらかしにしていた。以前就活を辞めて個人での制作に本腰を入れて集中しようと決断したのと、就活を辞めた理由の一つにチームでの開発に意義を見出せなくなったからというのがあるので、この約束は無しにしてもらうべきか……と悩んでいたのだけど、悩むだけで特に何も決断せず、チームメンバーに連絡もせず、なあなあにしてしまっていた。
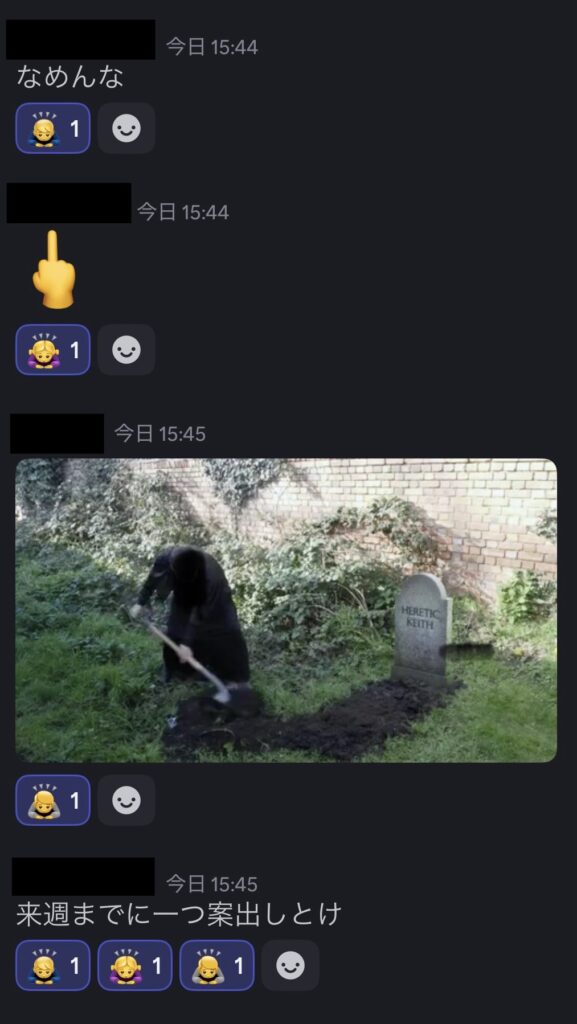
「無理だ」と言って謝罪したら、猛攻撃に遭った。
言い訳ではないけれど、企画って立ち上がるときは高揚感と場の勢いでとんとん拍子に話が進む反面、ポシャにするときはすごくカロリーが要るな。自然消滅も多いし。でも終わらせるその痛みを恐れて企画立ち上げに臆すのも違うから、立ち上げては潰しというサイクル自体は健全か。今回は100%僕都合で無しとさせてもらうから、すべてのカロリーを僕が引き受けて謝るしかない。
英語の最終課題をやろう。途中までやった。「あなたは幼い頃、よく何をやっていましたか?」という題に答える英作文の問題があった。
僕は幼い頃、ポケモンの指人形を使って物語を演じて遊んでいた。台詞を親に聞かれるのが恥ずかしいので、頭の中で喋りながら無言でやっていた。主な登場人物はボスゴドラ(父)とアーマルド(兄)、サーナイト(母)、プラスル(双子妹)とマイナン(双子妹)だった。展開にバリエーションはあれど話の顛末はだいたい同じで、ボスゴドラとアーマルドが、サーナイトやプラスルマイナンの安全を守るために、拷問を受けたり、トゲの山を登らされたり、積み木で作った「崩壊」に襲われたりするという話だった。とにかく屈強な肉体と男性性をもつ者が不可抗力によって血を流したり、辱めを受ける妄想ばかりしていた。特にボスゴドラが気に入っていて、アーマルドの肉体的負担をボスゴドラが肩代わりして、二倍の苦痛を受ける回もあった。三島由紀夫の少年期とまったく同じリビドーだ。幼稚園の時点でこの仕上がりは、期待が持てる感じですね……!
↑これを英訳すればいい?

アスパラガスの天ぷらを食らえ。これで切腹しようとしたらうけるかな。
ゲーム関係の人とゲーム関係の相談をした。ゲーム関係とは。ご飯めっちゃおいしかった!
最近のクリエイターは肩の力が抜けていますね、ということについて話した。何か大きなテーゼを世に知らしめるために作品を発表するわけではなく、自分を通して出力されるものを軽い手捌きで出品しているという感じがする。「私はオールドタイプが抜けきっていない人間なので、クリエイターとして今自分が発信すべきことは何か、みたいなところに実存的な悩みを見出してしまって、自分はクリエイターにはなれないんだと思い知ったことがあります」と言っていた。「クリエイターという存在をそんな大それた仕事人として見ないです」と僕が言ったら、やっぱり軽やかですねーと言われた。
SNSが普及して、その人のプロフィールを見て投稿を遡って見ていくだけで面白がれるようなものですかね? と言ってみた。作品が発する既存の価値観の塗り替え・表現史的な革新性を読み解くとかよりも、各クリエイターの生きざまや固有性から自然にアウトプットされたものを特に抽出せずにありのまま見ることが作品鑑賞のあり方として主要になってるのかも、みたいな。
「現代のクリエイター、肩の力が抜けている感」はわかるなー。命を削って作られた大作品よりも、のほほんとした制作スタイルで継続的にアウトプットされたものの方がよく見かける? ど、どうだろ。大テーマの作品が少ないゆえに「現代のクリエイター」を主語に語ることも難しい。SNSによってしょうもなくなった変化の一つとして、現代のクリエイターの間で、過度に反社会的なテーマなどは避ける危機察知能力みたいなのは共有されてしまった印象がある。みんななんとなくぼんやり触れようとしない表現領域みたいなのはある。血を滲ませてまで物議を醸すようなテーゼを主張しても、リターンが少ない時代なのかな。そういうのに言及したところで、叩かれるか市場から見向きされずに終わる。ゲームなんかは特に作家の手を離れて誤読されることが称揚されるメディアだから、そもそもテーマを込めることの意義が薄まっている。
みたいなことを広く浅く話した。まるで熱く語り合えた感じになったけど、こういう「ゲームの今」「クリエイターの今」みたいな話は、正直あまり興味なかった。これは現代とオールドタイプの違いというより僕個人の感覚だけど(という筆致がすでに現代人的なのかもしれないが)、何かの理想などについて「語り合う」という営みがそもそもそんなに楽しくない。独り言として自分の理想論を語ることはあるけれど、それをわざわざ共有の場に持ち寄って相互作用させたところで「へぇ〜、そすか」で終わるような感じ。摩擦を恐れているわけではない。創作論について直接語り合うよりも、「僕は小鉢料理が好きです」「へ〜、なんでですか?」みたいな指向性のない対話を重ねてその人その人の個別的なあり方・考え方を交換しあうほうが、クリエイター同士のコミュニケーションとしてはよっぽど食いでがあると思っているのだ。
帰宅。
即
寝。
色々とやってない。
でも土日は少し休みムードの予定です。
When I was a child, I used to play by creating stories with Pokémon finger puppets. I was too embarrassed to let my parents hear the dialogue, so I acted everything out in silence, speaking only in my head. The main characters were Aggron (father), Armaldo (older brother), Gardevoir (mother), and Plusle and Minun (twin sisters). Although the plots varied, the outcome of the story was almost always the same: Aggron and Armaldo would endure torture, climb spiked mountains, or face “collapsing structures” I built out of toy blocks, all to protect Gardevoir and the twin sisters, Plusle and Minun. The theme was consistently about strong, masculine figures being forced by circumstances to bleed or suffer humiliation. I was particularly attached to Aggron. There were even episodes where Aggron would take on Armaldo’s physical burdens, enduring double the pain. It’s the exact same libido as Yukio Mishima’s childhood fantasies. The fact that I was at this level as early as kindergarten… promising, isn’t it?
