14時に目覚めたときからパニックのようになっていた。頭がいっぱいだった。ただ、こうなった理由はわかっているつもりだったので、おそらく自分の力でどうにか解消できると思った。今日お友達と食事の予定があったのを、ひとまずリスケしてもらった。とりあえずご飯を食べて、横になりなおそう。一度だけ、無理にでも起きあがる必要がある。僕は土砂崩れみたいにリビングに転がり込んだ。
パートナーとツインピークスを見ながらパスタ食べた。彼が「ツインピークスって日本で圧倒的に人気だったんだよ」と言い、それに僕がエネルギー不足で「うん」と気の抜けた返事をしたら、彼はこっちを見て「大丈夫?」と心配してくれた。僕は「いや、」と言った。それ以上声を出せなかった。パートナーはそっとしておいてくれた。パスタを食べる音と飲み物を飲む音が静かになった。
横になった。考えが高速すぎて追えない。こういうのは取り合っても無駄なので、薬が回るのを待ちながら、呼吸などをしてやり過ごしていた。そしたら寝た。
枕元に置いてあったパートナーのスマホが光って、「いちごんこう」という人物からのメールが届いていた。放っておいたらスマホは暗くなった。どうでもいいなと思って、目を閉じてまた寝ようと思っていたら、パートナーが襖を開けて寝ている僕のところに来た。その後、近くに置いてあった雑誌をめぐって色々コミュニケーションがあった。パートナーは雑誌を手に持ちながら、「好きな女の子ができたんだよね」と呟いた。彼は「もちろんこれからもトロヤくんと過ごす時間の頻度は落とさないし、向こうも良識ある人だから、差別とかないし、今までどおりの関係性でいられるよ」僕は「これって夢?」と言った。彼は「夢なのかな?」僕は「いちごんこうって人でしょ?」「どうして知ってるの」「いや、メール通知がロック画面から丸見えだったぞ。その秘匿管理ができていないことがまず信じられないな」と僕は言って、これが夢であって欲しいと半分思い、もう半分は、この実感が夢であって欲しくないと思った。「好きな女の子ができたんだよね」と彼が言ったとき、僕はまず、「まあそういうこともあるか」と思った。愛は複雑で、人も複雑なので、世の中何があるかわからないからだ。ただパートナーが僕に隠れて他の人と性愛に関するなんらかのなんらかに及んでいたことと、その相手が女性であったことはあまりに僕の予想を超えていたので、これは夢かと思ったのだ。ただ、現実が予想を超えてくること自体は予想の範囲内だった。それに、「好きな女の子ができた」と今言ってくれたのだから、さほど隠してることはないのかもしれないし。
僕はこれが夢でないことを確認するために顔を叩いたり、部屋を歩き回って壁に身体をぶつけたりした。夢ではなかった。洗面所の鏡を見ると、僕の頭は半分くらいの面積が禿げていて、何かの病気の症状のように見えた。パートナーは仕事関係のZOOMを繋げ、誰かと話し始めた。相手は何やら女性の話し声だった。いちごんこうってこいつか? 彼女は彼の、仕事関係の知人なのか。「私は愛について、もっとニュートラルなかたちで人との関係を確かめてみたいんです。人と人の愛こそ、日本社会における既存の枠組みが無意識に刷り込まれている一番の人工概念だと思うので」などと言っていた。聞く感じ、いちごんこうは社会学的な研究テーマを持っていて、そのフィールドワークとして僕のパートナーにセックスアピールをおこなっているらしい(?)。僕は彼女がそれを本気で言ってるのか、それともパートナーを籠絡するための高度なアプローチなのか判別がつかなかった。ただ少なくとも、いちごんの利発な感じは、パートナー好みかもしれないなと思った。いちごんのアプローチはぶっ飛んでいるようだけど、パートナーは性格的にぶっ飛んだ人のことを好きになってもおかしくない。ただ僕には、パートナーは明らかに一時の興奮を刺激されて、それに籠絡されているように見えた。だからあきれた。絆されてるぞ。ちょっと安心もした。この件は一時的にハニートラップが奏功しそうなだけで、彼が言うとおり、僕に対する愛が揺らぐことはない気がした。僕が捨てられることはなさそうだ。でもやっぱり少なからず、僕は布団を抱えて大泣きして、叫んだ。
という夢を見て目覚めた。めっちゃ悪夢だった。悪夢を見たあとはだいたい思考がすっきりしているので、悪夢は好きです。僕は無意識のスペックを、結構信頼している。弱った僕の散らかった心内環境を、脳が整理してくれる。そのことを一番実感できるのが悪夢だった。悪夢は、無意識による荒療治の断片なのだと思う。実際、14時に目覚めたときのパニックは落ち着いていた。
ただちょっと驚いた。悪夢の内容が浮気に関することだったのが意外だったのだ。僕は、自分のパニックの理由は別件だと思っていた。昨日アップロードした半パンダの歌のことだと思ってた。あれで色々思い出したのが原因だと思った。しかし、脳が悪夢で濾して重点的に整理したのは、性愛にまつわる不安だった。それが予想外だった。
まあ悪夢の主題が浮気されたことだったからといって、本質がそれだとは限らないか。愛着とか自他境界の問題と考えれば、僕の予想していたパニックの元凶とも重なる。あんまり考えても仕方ないよね。思考ではどうしようもないキズの修復を無意識に委託したのだから、コンパイル後の納品物を思考で読み解こうとしてもしゃあない。なんにせよ、僕は回復した。よかった。
爪切って、ゆっくり過ごそうかな。ていうか、夢の中で夢かどうか確認する作業、役に立たねー。
寝室を出て、パートナーに夢のことを報告した。いちごんこうの社会学研究テーマについて話したら「それって俗に言うオープンリレーションシップってやつじゃないの」と言われた。僕は「俗に言ったらまあそうなんだけど、あなたはあくまで社会学的研究のための特殊なケースとして、僕と彼女と同時に付き合おうとしていた」と言った。
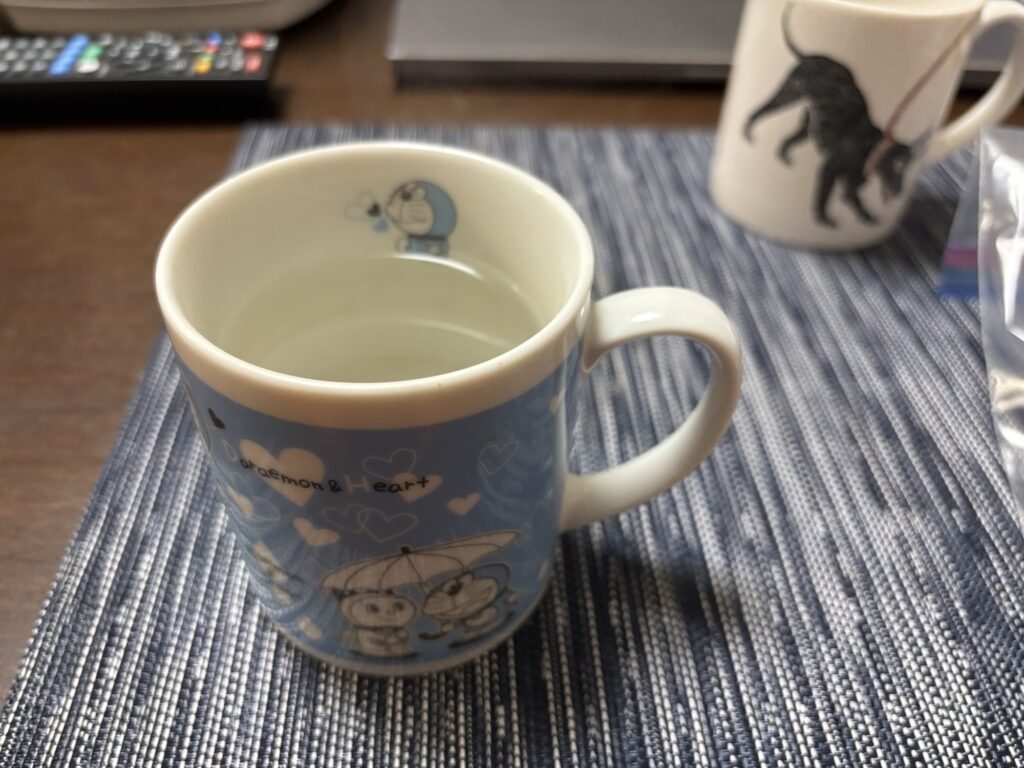
白湯入れてもらった。人生初の。一般に、一度沸騰させて冷ましたものを白湯というらしい。お風呂の湯をごくごく飲んでいるみたいで背徳感があった。おいしー!
スクワットした(まだしてないけど、これからする)。スクワットした(まだしてない)。スクワットした。
MBTI診断。のことを、流行りだしてからずっと、SNSであんまり面白くない使われ方をしているものだと思って、気にしないようにしていた。しかし思ったより息が長かった。SNSにとどまらず、ジョナサンの隣のテーブルの大学生らも各々のMBTIを軸に会話を広げていたりしている。16種類あるのに、よくそれぞれの特徴を覚えている。就活シーンにも時として取り入れられている(まじで)。一時の流行どころか、自認はあっておかしくないものとして定着していくのか? 自分の血液型を知らない人は珍しくないくらいにはちらほらいる。世代によっては、自分のMBTIを言えない人もそのくらいの存在感になっていたりするのかな。いくらもとの根拠が弱くても「A型は几帳面」「O型は大雑把」のように、人々に何度も宣言されることによって概念としての強度は高まっていく。人口に膾炙してしまえば言葉は実体を持ち、否が応にも役に立つものになってしまう。
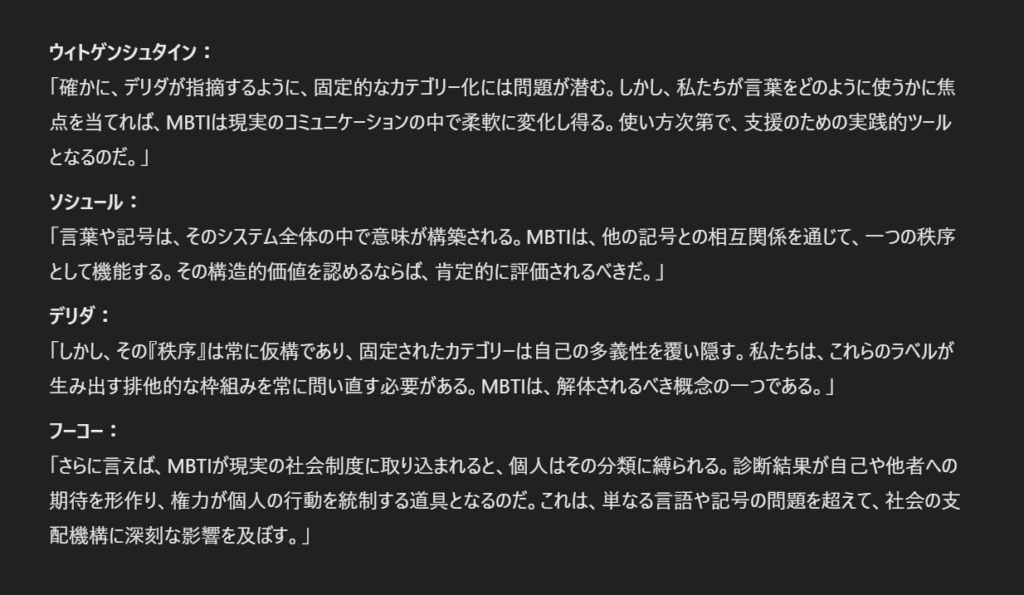
児童文学『世にも不幸なできごと』第6巻「まやかしエレベーター」の舞台となる”おしゃれな”街は、食べ物、服、感情などあらゆる物に「イン」と「アウト」がある。両親を失った主人公の三姉弟妹が新たな後見人のいるマンションを訪ねたとき、「暗いはイン」だったので照明はすべて落とされており、「エレベーターはアウト」のためわざわざ階段を登って最上階にいく必要があった。人々はインなものだけを持ち、アウトを持っていると街中の笑いものになる。しかしこのイン/アウトは目まぐるしく変わるもので、昨日までインだったサーモンが、今からアウトであることが報じられ、人々は一斉にサーモンを吐き出したりする。そもそも主人公たちがこの街に引き取られたのも「孤児がイン」になったからだ。
「雨男」「晴れ女」と話題にする人がいたとして、それをくだらないとは言いづらい。わざわざ一笑に付すことの方がある種の立場表明になってしまうからだ。同じように、いずれMBTIについて興味のない仕草をする方がしんどくなってくる未来が来たりして。
僕が今のところMBTIについて知ってることは、SNSにおいてはなんか、INFPかそうじゃないかが一番の関心どころらしい? ということだ。違ったらごめん。で、みんな興味あるってことは、INFPはさしずめ、弱者とか陰キャとか社不だとか繊細だとか、翻ってこだわりが強いとかアーティスト肌とか世の中の矛盾を許せないとか、そのへんの性格パターンと結びついているんでしょう……カスどもの思考回路など、お見通しなんだからな……!
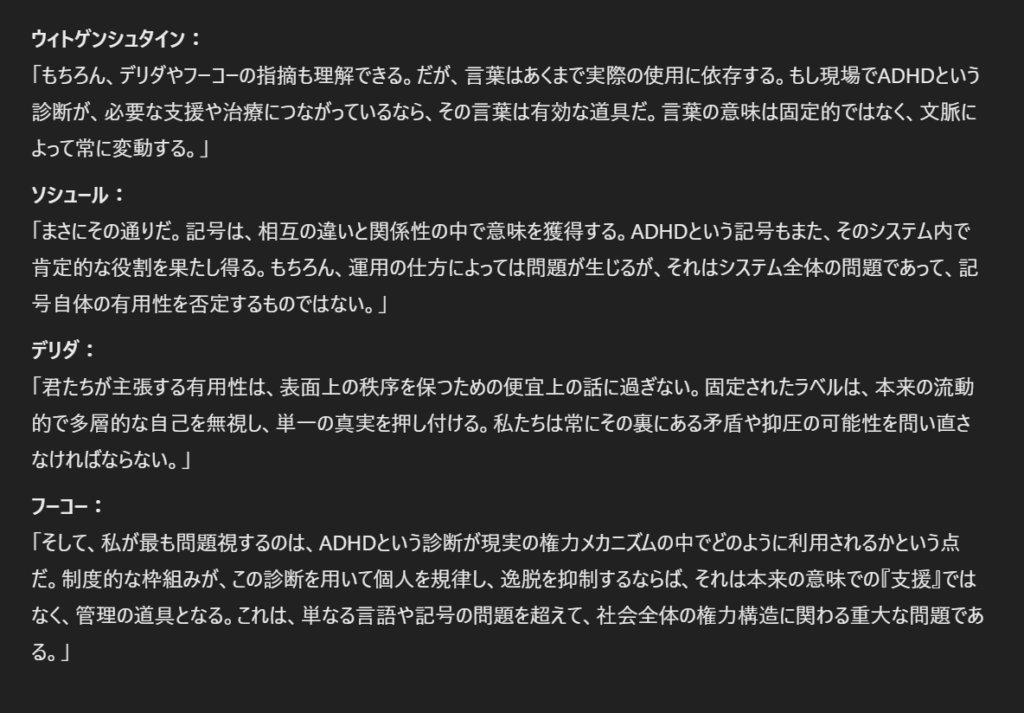
今はソファがインなので、ソファに寝そべっている。開発はアウトなので、Netflixを見ている。ソファに寝そべりたくてゲーム開発をしたくないとき「ソファがインで開発はアウト」と言う。言い続ければ、いつのまにか本当にソファがインで開発がアウトになっていたりする。
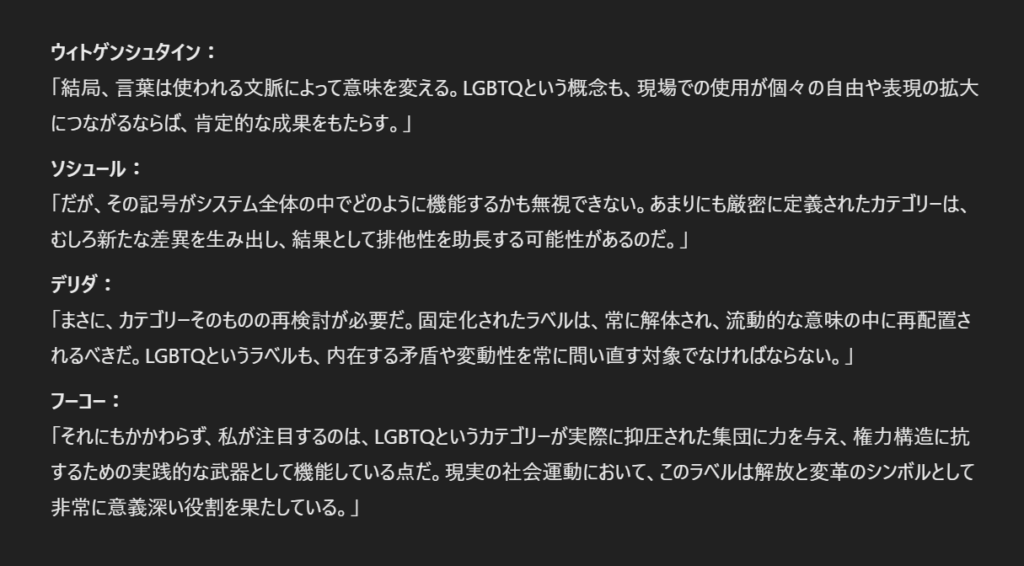
急に変わりたい。甘ったるいのは紅茶失格だ。
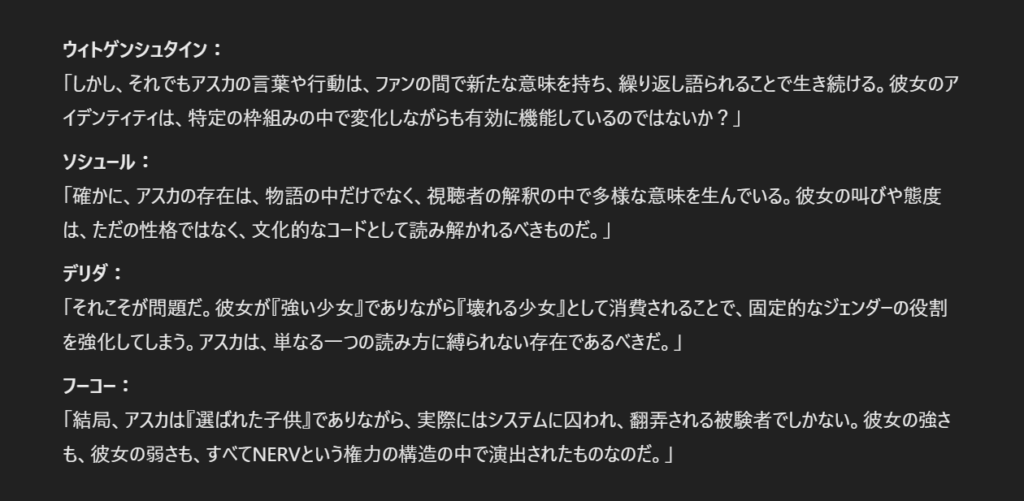
ずっとNetFlix見てる。『世にも不幸なできごと』を流している。最近日記で思い出しがちだから、久々に見ようと思った。原作小説が至高だけど、ネトフリのドラマ版も名作。映画もあるけど、そちらは微妙です……。
レモニー・スニケット作の『世にも不幸なできごと』は全13巻の児童文学だ。
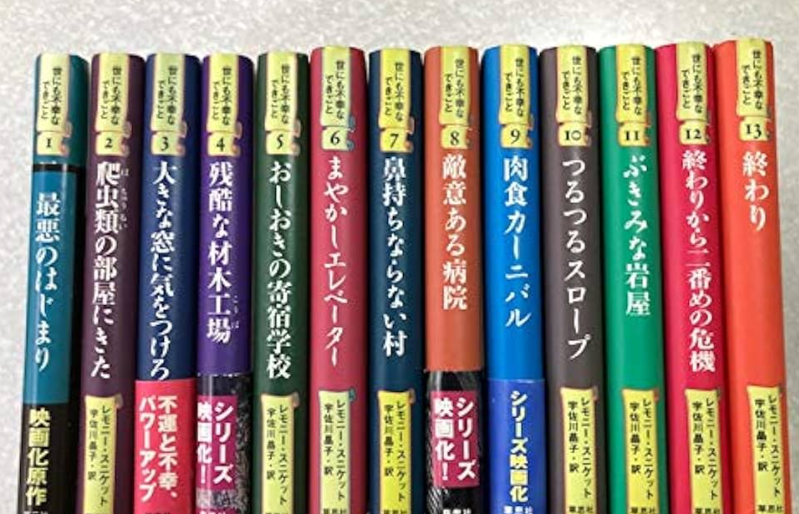
学校の図書室で↑の背表紙の並びを見た人、いますよね? デルトラクエストやダレンシャンに比べたら全然人気なかったけど、小一の僕が最初に手に取った初めての小説はこれで、かつ、ちゃんと決めているわけじゃないけどいまだに最も好きな小説作品のひとつだ。
初めの方は一ページあたりの文字数も少なく低学年向けと言えるけど、巻が進むにつれだんだん文字数が増えてきて、話も難解になってくる。読者の成長に寄り添う感じでいいな。
主人公はボードレール家の三姉弟妹で、14歳の発明好きのヴァイオレット、12歳で読書家のクラウス、歯が鋭い乳児のサニーだ。ある日海辺で遊んでいた三人は、知り合いの銀行員に「君たちの家がさっき燃えて、ご両親は亡くなったよ」と伝えられ、急に孤児になる。両親は多額の財産を残したが、ヴァイオレットが成人するまではその遺産は銀行保存になり手をつけられないため、三人はとある後見人のもとに預けられることになる。その後見人がオラフ伯爵という人物だったのだが、彼がこのシリーズの悪役だ。彼はボードレール家の遺産を狙っており、三人をあらゆる方法で捕えようとする。
オラフ伯爵から逃れるため、三人は新たな後見人の保護下に渡る。でもその後見人たちが毎回愚かだったり、精神を病んでいて自殺したり、オラフの策略で殺されたり、騙されて三人を殺そうとしてきたり、そもそもオラフとグルだったりと、健全な環境に落ちつくことが一度も無く、毎巻なんだかんだ生活は破綻して、また別の後見人のもとへ渡される……という流れの繰り返しだ。
いろんなテーマが織り込まれていて、一口に魅力を語るのはむずい。
作者は故ボードレール夫妻と親密だった謎の人物(レモニー・スニケット)という体で、この小説は現在行方不明の三姉弟妹の冒険の調査記録として語られている。作者は自分が語っていることの顛末を知っているため「この物語はバッドエンドで終わる」と1巻の初めに書いていたり、新たな人物が登場したときに「この人物はn章で殺されることになるのだが……」と地の文でネタバレをしたりしてくる。登場する大人たちと同じく、作者も欠乏を抱えた神経質な性格であり、語りの途中で自分が書いた言葉の意味について自分でつっかかったり、急にナーバスになったり逡巡したりして、物語の語りを遅延することがある。
『世にも不幸なできごと』は子供向けの本であることをあくまで大事にしながら、言葉や意味、記号の力を表現している。毎巻同じパターンを繰り返す構造、明らかに戯画的で物語にコントロールされたようなふるまいをする大人たち、それとは対称的に「発明好き」「読書家」「赤ちゃん」というキャラクター属性を解体し、本当の意味で大人になっていく三姉弟妹。
三人は冒険を進めるにつれ、繰り返す自分たちの最悪な人生の背後に暗躍する大きな物語の存在を自覚するようになる。謎の秘密結社の存在、オラフと両親の間にあったらしき過去のドラマ、皆が口々に話題に出す「砂糖壺」という謎のアイテム、そして「自分たちの両親が本当に死んだのか」という謎。なにせ両親の死は、銀行員の口によって告げられただけにすぎないのだ。不可解なことが、裏ですべてつながっているような気がしてくる。背後で暗躍するその何かは、必ず「V.F.D.」というイニシャルで略せる単語の形をとって、物語上にちらつく。でも毎回、その実態に近づくことはできず、三人も読者もやきもきする。大きな謎を解き明かしたいのに、物語は意味深さをただ転がして、謎は謎のままであり続ける。
この小説を手に取って冒頭を読んだ人は、燃えた家と死んだ両親というのは「孤児たちの物語」を開始させるためのマクガフィンだと捉えるだろう。それは小学生でも自然に受け容れられる。でも、だんだん物語の内部に具体的な謎の輪郭が現れはじめてくる。だんだんと読者は「両親は死んでいないかもしれない」という考察の虜になってくる。でも真相らしきものに近づいたと思いきや、『世にも不幸なできごと』はやっぱり答えを示さず、これらをあくまでマクガフィンとして捨て去り、読者を突き放すのだ。これをうんざりするくらい繰り返す。
小学生がこれを理解するのは難しいと思う。「両親は死んだのか、生きているのか」は必ずどちらかであって、読み進めればきっと明かされるだろうと期待する。しかしその期待は一向に満たされない。物語の大人たちが追い求める砂糖壺すら、一向に出てこない(この砂糖壺の存在が、この小説がマクガフィンを操作するメタ小説であることをわかりやすく伝えているのだけど、小学生がそれを読み解くのは無理だ。この物語を読み終えて何年か経った未来に、ふと振り返って気づくしかない)。
僕は、この小説が児童文学として図書室に存在していることが素晴らしいと思う。親を亡くした三人の子供が、物語の操り人形であるろくでもない大人たちに翻弄され、手ごたえのない世界に期待しては幻滅する。冒険の先で三人は記号ではなくなり、主体として存在する自分に勇気を持つようになる。この読書体験は、不確かな大人のもとで育った子どもが、内側に抱えた自他への不信感を乗り越え、成熟するために必要な発達の過程そのものなのだ。人生が決して自分を満足させてくれるものではないこと、それでも小さなリアリティを見つけ、確かな価値を見つけていくことはできること。それを知ること。
で、今これを書きながら泣きそうになっちゃっているのだけど、『世にも不幸なできごと』の物語にはあと一つ、重要なお約束がある。毎巻かならず、何らかのかたちで図書室(本がたくさんあるところ)が現れるのだ。図書室との出会いがいつも、三姉弟妹にピンチを切り抜けるアイデアを与えてくれるのだった。それは生きることに苦労を感じる子供が、学校の図書室で救いとなる大切な本と出会うのと同じだ。僕がこの本を手に取ったのと同じだ。
アー
今流し見していたドラマ版でちょうど、図書館司書がライオンに食われて死んだ感じになった。なんて嫌な話なんだ。オラフが「ここに本がたくさんあって良かったな。引火しやすいから」と言った。本を燃やした。大人たちを、図書へのアクセスを阻む存在として対置しているんだな。
アー
6時? 今、朝の6時なの?
何時でもないと思ってた
今日ってもう 終わる感じですか?
そんな
