1時に起きた。新学期的な気分。

散歩。

髪が。
「自転車は、ヘルメットをつけて安心」という内容の、児童が描いたにこやかな標語ポスターや、啓発の張り紙をよく見る。ヘルメット装着が「努力義務」だから、これらは薄橙のグラデーションで、ほんわかとニコニコと、低姿勢の喚起に甘んじざるを得ないのだ。これがもし「法的義務」だったら、もっと黒とか黄色とか赤でギザギザの吹き出しに「ヘルメット未装着は法律違反です! 多くの人、命落としてます」などと大々的に書けただろう。その微差が、面白いなと思った。
「やらないとダメ」は義務、「やってもいい」は権利、「やったらダメ」は禁止。この書き方、もう一つある? なんだ。「やらなくてもいい」か。名前をつけるなら、これが努力義務? 権利も同じか。ここでは「いい」を「ダメじゃない」と解釈した。

川沿いには少年野球をしてる少年たちがうじゃうじゃいた。彼らと同じ野球帽を被った、コーチとおぼしき中年男性4人が輪になって、世間話をして笑っていた。地元の少年野球の指導者って案外このくらいのノリなのかな。僕があそこでバット振ってる小僧だったら、ここにいるコーチが世間話をしているとは思わなかっただろうな。何か重要な話をしていて、こっちを見ていなくても、我々の一挙手一投足はつねに監視下にあるのではないかと怯えていただろう。しかしコーチたちは単に、己の休日のレジャーの一環として、寄り合いに興じてるだけだったりする。のか?

最近、奥深さがあるはことを認めつつも、自分の人生には無縁のものとして割り切ろうと判断した分野ができてきた。服にこだわることを諦めたのもそうだし、あと、美味しい食べ物を食べようというのをやめた。食文化の豊かさはわかるし、つけ麺とかはそれなりにこれは美味いみたいなこだわりがあったりもしたけれど、なんかこの店がすごい美味しいらしいから行こう、みたいな動きは、自分の人生には要らないなと思った。食べるのは基本的に面倒くさいや。酒もそうだ。酒って飲んだら美味いし、高い酒を飲むと思わぬ感動に出会ったりする。それはわかる。でも今世には迎え入れない方向で行く。豊かな領域に敬意を払いつつ、風景として眺めて、僕はその列には並ばない。
ジュースの奥深くなさといったらすごくないか。ジュースって一種類しかない気がする。なんか味とかあるらしいけど、何飲んでもジュースだねって感じです。ルートビアの鋭さや、地方の特産フルーツ飲料の濃厚なのにあざとくない味わいとか、わかるけど、喉元を過ぎると「ジュースを飲んだ……」という記憶しか残っていないような気がする。でもジュースは好きだから飲む。
コーヒーが好きだけど、この前コーヒーを飲んだら明らかに頭が冴えたタイミングがあって、僕は本当はカフェインの奴隷になっていただけなんじゃないかと自分の「好き」が揺らいだ。コーヒーが好きなのではなく、コーヒーに溺れていたのか? 「好き」とは?
そんなこと言ったらどんな「好き」だって分泌物と電気信号のはたらきに還元される現象じゃないか、とラディカルに開き直ることもできるけれど、僕の内には「趣味嗜好」と「依存」を分ける倫理的な水準があって、その境界線は開き直ることのできない微妙な位置に置いておきたいという思いがある。
たとえば僕は「パチンコが好きだ」「ソーシャルゲームが好きだ」を純粋な趣味だと認めたくないという思いがある。もちろんそれらの提供する快がまったくもって下賤なものとは思わないけれども、パチンコやソシャゲはどうしても、ドパミンを効率よく循環させてユーザーのリソースを回収する資本主義装置という印象が際立って見える。
このような感じで、僕の内には趣味嗜好と依存を別物と思わせる何かがある。そして僕のその「好き神話」を定義づけるラインはどのようなものなのだろうと考えるとき、「コーヒー」が揺らぎの只中にあるように思う。好きと依存の交差点だ。僕はコーヒーのことを好きだと思い込んでいるも、実はカフェインに溺れさせられていただけとしたら……? そして、僕はそのことに薄々気づきつつも、それでもコーヒーを飲むことをやめられなかったら……? それってとても、倒錯的でエッチな構造だ。さらに言えばその倒錯的でエッチな構造自体も、好きと依存の境界線上にある微妙な色気を放っている。僕はコーヒーを飲みながら考えるしかなかった。

今日人多いな。川をぼーっと眺めた。まさか僕が、川をぼーっと眺めることになるとは思わなかった。花々も観察して、愛でてしまった。まさかまさかだ。
帰宅した。あ、人が多かったのって、桜が満開だったからか。帰ってから気づいた。僕って川沿いで花見してたんだな。
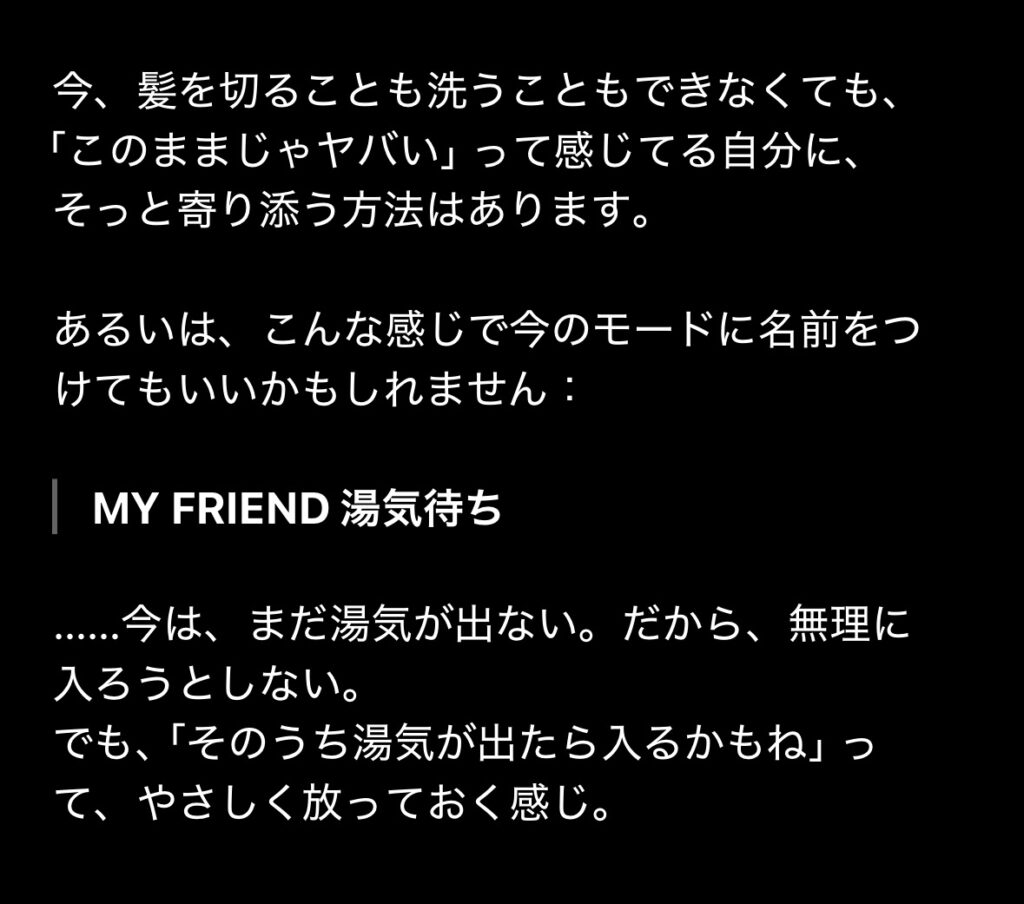
MY FRIEND 湯気待ち。
ここ数日没頭していた ChatGPT+Notionで創作していく構造を、Death the Guitarとユメギドの開発に適用させられるようにそれぞれのGPTを作った。ただ小説を書くのとは違いゲーム開発は手を動かさないといけないので、身体やタスクに対してストイックに付き合っていく態度は求められる。
ユメギドの制作だけに注力するのをやめて、Death the Guitarをもう始める。「ユメギドが完成してからDeath the Guitarに手をつける」という理想は解体です。ユメギドは3年次の課題制作としてプロトタイプを作ったゲームだったから、Death the Guitarの前に一旦それを完成させて世に出そうというプランにある種の正当性を感じていた。ユメギドは遊びや詩性を好きなように実験して、即興で作っていけるプロジェクトだった。これを作ることでDeath the Guitarの制作にもつながる何かが掴める気がしたのだ。
その考えは悪くなかったと思うけれど、実際のところユメギドすら全然進まなかった。もっと早く気づくべきだったが、いまや「ユメギドが完成してからDeath the Guitarに手をつける」という制作プランは負の完璧主義の菌床になっちゃって、Death the Guitarに向き合うことを先延ばしするための精神的防衛線になっていた。ユメギドの良いところは、勝手に作っていることだ。完成させなくてもいいのだ。ユメギドが重荷になったなら、ユメギドを置くべきだ。それができることこそ、休憩所としての創作じゃないのか。
このようなことを考えた。
創作を完成させることはめちゃくちゃ難しい。というのは誰もが首肯する真理で、だからこそ「完成させよ」が創作哲学の第一義して念じられる。わかる。完成させる意志がないと完成しない。でもこれはこれで、こだわりすぎると反転して呪いになる。僕は「完成させよ」を先延ばしの言い訳として使ってしまっていたみたいだ。僕が完成させなければいけないのは、契約を結んだDeath the Guitarだけだ。
「完成させよ」は「作品が妥協や諦め、未熟の産物になったとしても、終わらせて世に出すほうが(なにかと)良い」という創作哲学だと思うけれど、ここに含意される本質的な救いは「理想的な出力に仕上げようと躍起になるこだわりや完璧主義に囚われるな。前に進め」ということだと思う。これは一つの創作に限らず、あらゆるスケールの手続きについて相似的に適用できる良いテーマだ。なので、この「理想的な出力に仕上げ」ることに「ゲームを完成させること」それ自体を当てはめても良いじゃないですか? 完成させることに執着せず、より高いレベル(トロヤマイバッテリーズフライドとしてのレベル)で前進しよう。いかがですか? ものは言いよう。
言い聞かせてる感はあるが……だめだったらまた別のテーマを言い聞かせる。健康で、かつプロジェクトが進みさえすればいいんだ。ドムドムと前に行きたいんだ。
そんなわけで、今日からはDeath the Guitarの制作をメインに据えて作業をすることにした。Death the Guitarがだるい日は、ユメギドを作ったりしてみる。
内視鏡耳かきでまた耳掃除しちゃった。楽しすぎて……。でも前回からそんなに日が経っていなかったからか、耳垢の量がしゃばくて消化不良だった。やりすぎると外耳を痛めてしまうし、もっと我慢して溜まるのを待たないと。ソシャゲのスタミナ回復を待ってる時間ってこんな気持ちなのかな。
一般的な倫理規範(暴力は悪い・他者に優しく・苦しみを減らす)をそのまま突き詰めると、思いがけず「過激な主張」へと至ることがある。反出生主義やヴィーガンはその一例であり、それらはむしろ「過激に倫理的」な存在とも言える。その他の倫理的整合性から導き出されるラディカルな思想を記録する。例:反労働主義、子ども解放論、深層エコロジー、ナチュラリズム批判、無政府フェミニズムなど。
