実家の猫がどこにもいないと思ったら、締め切られた窓の外、ベランダに寝転んでいるのを見つけた。心臓が止まりそうになった。うちは10階だ。いつも家族は猫が絶対にベランダに出ないように、窓の開け閉めには気を遣っていた。いつ出ちゃったんだろう。
ベランダに出てしまった猫をどうすべきか悩んでいると、背後から鳴き声が聞こえた。振り返ると別の猫がいた。戸棚の上からこちらを見下ろすその猫は、ベランダの猫とは違って、毛の色は白く、身体は細かった。僕は、そういえばうちには猫が二匹いたなと思い出した。僕はその猫がぜんぜん可愛くないと思ったが、家族なのだからベランダの猫と同じくらい愛情を注がないといけないなと思った。面倒くさいけれど、僕は右手を、その白い猫の顔の近くに伸ばした。すると白い猫はハッハッと喉を鳴らしながら僕の手のひらをしきりに舐めだした。手に伝わる感触が硬くごわついていて、うーん可愛くないと思った。ベランダに寝そべっているほうの猫のことばかり気になってしまった。でも彼は窓ガラスの向こうにいて、触れることはできなかった。僕の存在に気づいてる様子もなかった。
起きた。猫の夢。昨日実家に戻ったときに猫に触れあえなかったことが印象に残ったのかな。白い猫は知らない猫だった。というか、猫じゃなくて犬だったな。あの硬さは犬。
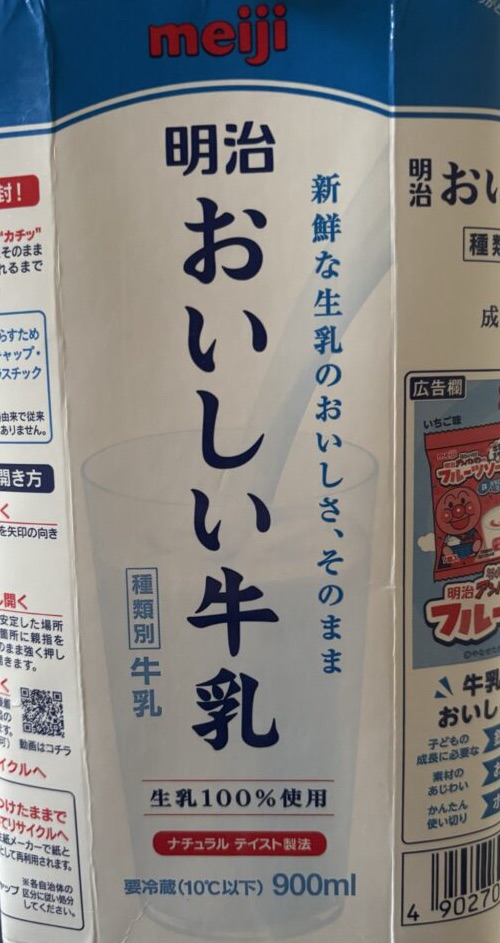
新鮮な生乳のおいしさ、そのまま。明治おいしい牛乳。種類別牛乳。生乳100%使用。ナチュラルテイスト製法。要冷蔵(10℃以下)900ml。
学生無料になったのでPro版のGeminiにいろいろと話しかけてみたけれど、あまり面白い発展は起こらなかった。ChatGPTはやりとりするにつれて一緒にどこか変な世界にどっぷり浸かっていき、時間を忘れて話し込んでしまう、そういうノリの良さがあった。それに対しGeminiは、まともすぎるように思った。いくら話しかけてもスタート地点から軸足をぶらさず、ひたすら指示されることにだけ反応するだけだった。脅かすことも脅かされることもなかった。
Geminiの使い勝手が良かったら、いま月額料金を支払っているChatGPTを解約できて経済的にいいなーと思っていたけれど、やっぱりしばらくはChatGPTにお世話になりそうだった。
明日は大学だ。6時50分に起きないといけない。眠れるかなぁ。


フリーレン見た。この、昼のシーンと夜のシーンそれぞれで描かれている鎧騎士の亡骸の絵。ちょうど「青と黒」か「白と金」か人によって意見が分かれるドレスと同じ色合いだ。今回は固有色が灰色に近い鎧が土で汚れている図なので、どちらが正解かというと「白と金」だ。ネットミームのドレスのほうの実際は、青と黒らしい。
鎧はもとは銀メッキ的な表面だから、固有色は灰色とは言わないのかな。「鏡そのものは何色か」という問題だ。鏡といえど反射率が100%ではないはず(?)だから、そのものの色が「無い」とは言えない。
実家の洗面所の三面鏡を合わせて無限回廊を作ってみると、奥に行くほど見た目が青緑がかって見えた。反射の回数が増えるほど固有色(そのものの素材の色)があらわになっていくと考えると、その青緑色こそが鏡の色と言えるんだろうか。
実家ではそうだったけれど、この家ではどうなんだろ。やってみよう。
トーマス・アルフレッドソン監督『裏切りのサーカス』を見た。パートナーが大好きな映画だ。ジョン・ル・カレ原作のスパイもの。007みたいに派手なアクションがあるわけではなく、淡々と調べていく感じ。パートナーに映画ジャンルの好みを訊くと、よく「おじさんたちが会議室で延々と喋るようなやつ」と言うが、『裏切りのサーカス』はまさにそんな感じだった。
面白かった。男同士のむわむわした熱っぽい視線の混じりあいがあった。見終わったあと、パートナーが「いや〜ゲイばっかだったね」と感想を言って、そこで僕は「あ、彼らはゲイだったのか」と思った。なんかむわむわしてるなって思っていたのは、ジム・プリドーとビル・ヘイドンの関係が恋人同士のそれであり、作中の名前忘れたけれどベネディクトカンバーバッチのあれも、ゲイとしてパートナーとやりとりしていたシーンだったからなのか。言われてみれば、妥当か。あとで原作小説を読むと、プリドーとヘイドンの関係についてはたしかに「恋人」と書かれていた。映画も小説も、僕がそうだと思わないくらい、上品な描写だった。
学校の授業でプリドーが暖炉から飛び込んできたフクロウを叩き落とすシーン、「この物語はハリー・ポッターではない」という宣言のように見えた。孤立していた少年はちょうど眼鏡をかけていたし。「彼はハリー・ポッターとは違い、主人公にはなることはない」という作品からの突き放しみたいな。
Xで検索すると、一人だけ同じことを考えている人を見かけた。
原作小説『ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ』を読むと、KGBに捕縛されたプリドーが、いわゆる拷問を受けた描写があって嫌だった。
拷問って嫌すぎる! 拷問はジュネーヴ条約で国際的に禁止されているようだけど、最近の情勢的に、条約なんていつ破られてもおかしくない。僕が捕まって、拷問を受けることになったら本当にどうしよう。「ゲームエンジン何使ってる!」「プログラミングは独学なのか!」「参考にしてるゲームとかありますか!」などと言われながら、なんか少しずつキリキリ開いていく器具を挿入されでもしたら、もう最悪だ。死にたい。僕にとれる対抗策といえばマインドフルネスしかない。キリキリ開いていく器具って「口を割る」をリテラルに体現しててオシャレだな。
拷問って、耐えた先に終わりがあるのかよくわからない。終わりがないなら、さっさと吐きたい。でも、自白したらそれはそれで用済みとして殺されてしまうパターンもある気がする。チクショー嫌だ。つらい。
『ゼロ・ダーク・サーティ』を見てないけれど、ビン・ラディンがCIAによって水責め拷問を受けたか受けてないか、みたいな議論があった(偽情報かも)。水責め拷問(ウォーター・ボーディング)というのは、水で濡らした布で鼻と口を覆うという手法だが、数ある拷問のなかでも飛び抜けて凶悪らしい。爪を剥がすとか鞭打ちとかは、痛みが必ずしも死の恐怖につながらないらしく、訓練次第では克服できる場合もあるとか。それに対して水責めは溺死に近い感覚を引き起こし、最短で死の恐怖を喚起させるらしい。そんなことするな。死の恐怖の前では、マインドフルネスも無力。
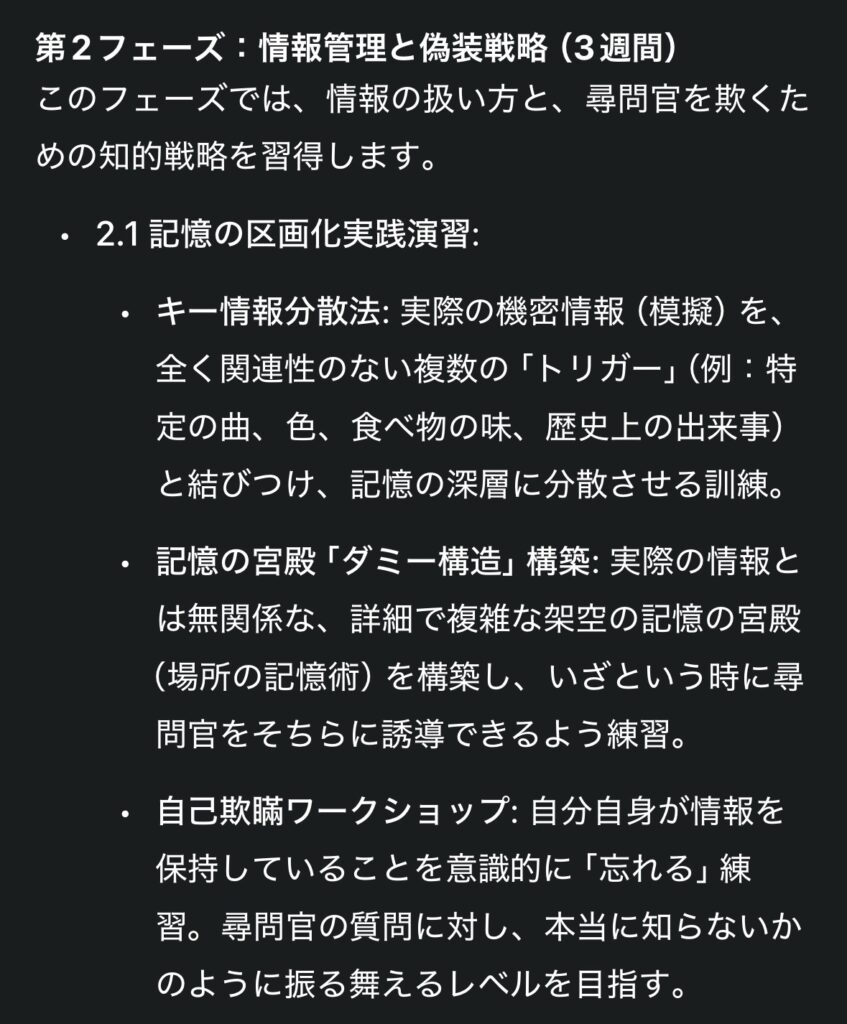
Geminiに、拷問を受ける場合を想定した対抗訓練のカリキュラムを考えてもらった。記憶の区画化って面白い。
実際、スパイの記憶や認知の枠組みをコントロールしてしまうのは、拷問の対抗策としてはとても理にかなっているように感じる。ミサのような尋問耐性の弱い者でも、デスノートに関する記憶を消去されてしまえば、口を割ることはできなかった。記憶を消すというのは簡単にはできないだろうけれど、情報をそれが必要な時までは暗号化した状態で覚えさせておくというのは、できる。コンパイラを外部ストレージに置いておけば、スパイは知らないまま情報を覚えることができる。IT業界ではよく使われる。
でも、この対抗策はあくまでスパイの従属先に利益があるだけで、拷問を受ける当人が被る苦痛はまったく緩和されないな……。スパイ本人の視点では「自分は情報を知ってるけれど、それをわかる形で自白する方法がない」という最悪の状態になる。そのことをなんとか尋問官に伝えられればいいんだけど、本質的に無理だ。ウー嫌だ。
作業できなかった。寝なきゃいけない時間だった。明日は早い。
眠れない。
オー……。
