昨日は往復44kmくらい自転車を漕いだからたっぷり疲れたのに、今日は早朝4時に目覚めた。4時間くらいしか眠らなかったのか。疲れが取れていない。”リズム”の反逆がもう始まっている。二度寝を二度しようとしたが、いずれも眠れないまま時間が過ぎるばかりであった。
しょうがないのでBlue Princeをやった。エンディング後もやることいっぱいある! 忙しー。ネタバレになるから書けないけれど、□□□□□□□□□□□□□□□□□□?(ネタバレになるから書けない)
このまま寝るか寝ないか、寝ないならやるか休むか、みたいな逡巡に、精神リソースを使うのをやめようと思った。何もできずにため息をつくだけの一日になるだろう。そういう日にかぎって体調を崩しがちだし。”リズム”がすべての鍵を握っている。Rhythm(流暢)。
ヴォワーと勢いで家を出た。9:55に作業場にやってきた。疲れている。眠い。だがやる。Discordの作業通話につなぐだけでもやる。
GPT-5が出たみたいですね。最近ChatGPTはCursor経由で使うことが多いからか、あまり違いが判らなかった。課金してすぐのころは毎日人生相談や込み入った自慰行為みたいなことの相手に使っていたけれど、最近はもっぱらプログラミングの補佐。
作業場で1時間ほど作業できたが、眠たさが本当のやつになり、瞼が戻らなくなってきたので荷物をまとめて退散した。照りつける正午。自宅に舞い戻った。豆パンを食べた。たとえ1時間でも、作業場まで足を運んで作業ができたのは良いです。最善の動きかただったと思う。
だが困ったことに、帰って布団入るとまた眠れなくなっちゃった。笑えます。
眠くなるまで本を読んだ。國分功一郎『中動態の世界』を少し読んだ。言語学的な視点から「意志」や「責任」というものにまつわる哲学を見ていく本だと思われる。スピノザは自由意志を否定しただけで、「意志」の存在はむしろ固く支持している。ただ、意志は行為の原因となるものではなくて、行為を振り返って事後的に現れる「効果」の一つに過ぎないことを強調している。というところまで読んだ。出来事を「自分の能力が引き起こしたことだ」と感じられるのが意志、みたいな?
実は多くの言語は、能動態と受動態という区別を持たない。動詞にこの二つの態がある(そしてこの二つしかない)のはインド=ヨーロッパ語族の一部の言語だけのようで、しかも歴史的にも比較的新しい文法規則らしい。でも、英語や日本語のような(日本語ってインド=ヨーロッパ語族じゃないよな)能動-受動の二項対立に馴染んだ言語の話者は、この対立でものを考えることが当たり前になっている。能動と受動の区別はその行為に「意志」や「責任」の所在を見ている。けれどこの観点は時として、現実の事象をとらえきれないことがある。アルコール依存者は自分の意志でアルコールを飲んでいるのか、犯罪者の責任能力は如何にして計られるのか、とか。
トロヤくんはいったい、さぼりたくてさぼっているのか、さぼってしまっているのか。遅刻しているのか、身体によって「遅刻されている」のか。生きているのか、生きざるをえないのか。実際のありさまは、日本語じゃ表現不能なのかもしれないですね。幾度となく親から「甘えるな」と言われてきたり、自分に言い聞かせてきた人生なので、心当たりがある。
心当たりを感じていたら、寝た。
起きたら姉がNight in the Woodsの配信をしていた。完結した。いいゲームだったね……。あとオープニングが面白かった。姉って変な人だな。
今やっているアメリカ産ノベルゲームが、面白いくらいNight in the Woodsと似たような話をしている。これってノベルゲームの類型なのかも。
アメリカの二十歳前後の主人公が、大学を離れて故郷の田舎町に帰る。そこはかつて鉱山資源の産地として発見され、急速に人が集まってできた町だった。しかしいつしか、工業問題や都市化・情報化・移民雇用の波によって、衰退してしまった。鉱山労働者やその子孫たちは、失ったかつての仕事の実感を取り戻すため、地元の誇りや家庭を守るために、祭など催事に躍起になったり、子どもに抑圧的なふるまいをしたり、宗教カルト的な連帯を作って外部からは理解されがたい因習を維持するようになった。
どちらのゲームも大体こんな感じ。こういったたぐいの題材はよく見る。アメリカだと、トランプ支持者に多い労働者層や、リベラルの波に生きづらさを感じるアングロサクソン系の人々が背負わされた物語という感じがする。彼らの保守思想がなめらかに陰謀論やカルトへとつながっていくのは、よくあることなのかな?
Night in the Woodsは、彼らのような労働の実感を失った大人たちと、発達障害やアダルトチルドレン等の理由から社会との摩擦を抱えて生きがちな性質を持つメイなどの若者たちが、比較できるように描かれている。そこが美しいように感じる。発達障害も、労働強度の高まって求められるスキルが上がってきた社会や資本主義にキャッチアップできなくなった者たちだ。社会から取り残された鉱山労働者たちに似ている。メイもビーもグレッグもアンガスも、それぞれの生い立ちや環境のなかで、日々の実感を失っている。世代間のそれぞれのシリアスな問題が、分かり合えないまま続いていくね……っていう空気がよかった。
日本のノベルゲー・ギャルゲー・エロゲーでもこういう題材はめちゃ多いよね。単に因習とエロの相性が良いってだけの話ではないだろな。今は『光が死んだ夏』アニメがとっても面白いです。『ダンダダン』のジジをめぐる話もそんなもんだったな。
動画の2:19:18くらいで、グレッグが「ドアはずっと壊れっぱなしなんだよ。」と言った。それで、ゲーム冒頭のバスターミナルでドアを直していた清掃員のことを思い出した。

「ていうかおっさん、誰? ここの清掃員?」
「らしいな。」
「何する人?」
「このドアを直す人。」
「そんだけ?」
「なワケねーだろ。」
この清掃員、隠れキーマンという風情でちょくちょく出てくるので印象に残る。この人もポッサムスプリングで一生を終わらせそうだけれど、町の保守派中年たちの連帯にはコミットしていないような気がする。彼はただ、清掃員の仕事にただひたむきで、それに手応えと日々の生きがいを見出して、自足しているように見える。この人がNight in the Woodsの中で一番、理想的なロールモデルというか、制作者から見た「正解」のかたちなんじゃないか。
メイはつくづく破壊の子として描かれていた。この清掃員のように生きること。すなわち「ドアを直す人になる」ことが、いつかメイが辿り着く最高のキャリアだったりするんじゃないかなーと思った。
良いゲーム!
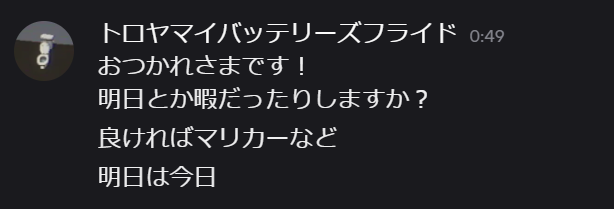
急に、お友達にマリカーやりませんかと誘ってみた。すると返事が来て、ウチ来る? と言われた。行くと言った。先方は明日彼のパートナーさんと遊ぶところだったらしく、僕もその人とはいつか会ってみたいですと話していたので。ちょうどよい機会かと。行けたら行けるかも。
パートナーさんは英語話者だから、英語で話すことになる。緊張する。僕は英語がろくに話せない。torture(拷問)という語はラテン語のtorqueo(曲げる、ねじる)から来ていることしか知らない。
会話で使えそうな言葉! 検索。
Uh-huh?(それで?)
What’s up?(どうしたの?)
Let me see…(ええっと……)
How can I say…(なんと言えばいいか……)
I’ll tell only the truth from now on.(これからは本当のことしか言いません)
Enough has been argued on this subject.(この件に関しては、もう十分論議がなされている)
All you have to do is sign your name here.(あなたはただここに署名をしさえすればよいのです)
一夜漬けでは無理があるようだな。寝る。今日は1時間だけ作業ができた。
明日起きて、時間あったらDeath the Guitarの開発をしよう。少し考えたけれど、Death the Guitarの今作っているワールドだけを切り取って、itchに出してみようかな。面は無限に続く仕様にして、死んだら終わりのスコア制にする。ストーリーも無しで、気軽に遊べるアクションゲームとして。プロトタイプというか、パイロット版? みたいな。一度、人に遊んでもらって、手触りを見たい。実感を取り戻したい。
