タモリがブラタモリで僕の地元を通ったらしい。僕はすぐ「タモリさん、改めて案内しますのでもう一度こちらに来てください」と連絡した。タモリは翌日に来た。僕は寺の階段で、緊張して待っていた。タモリが登ってきたのを見るなり、慌てて立ち上がって挨拶した。「わざわざ来てくださって、本当に嬉しいです」タモリは「いやなんの、若者に来いって言われたらね、つい来たくなるもんですよ」僕はタモリと目線の高さを合わせるため階段を一段降りたが、それをするたびにタモリは自分も一段下がった。僕をからかっているつもりなのか、失礼を感じて憤慨しているのか、そのどちらかわからなかった。タモリは「それであなた。こうやって僕を呼び出したってことは……」と言った。「やっぱりわかりますよね。そのやっぱり、タモリさんに来ていただけるなら、最大限のおもてなしをして、レジスチルの方を…」と僕は下卑た笑みを浮かべた。タモリはポケットモンスターシリーズのレベルデザイナーだった。僕はかねてからレジスチルを環境トップの座にどうにか持っていきたかった。種族値を補正するなり、わざを追加するなりしてもらいたくて、こうしてタモリに連絡をとるチャンスを待ちかねていたのだ。タモリは僕のそんな思惑など見透かしていたかのように「レジスチルの方はね、僕も考えてますよ。それじゃなきゃあ、こんなところの若者まで会いには来ないでしょう」と言い、からからと笑った。僕も追従笑いをした。「こちらへ来なさい」タモリは歩き出した。連れてこられたのは、『HP』『こうげき』『ぼうぎょ』『とくこう』『とくぼう』『すばやさ』を司るマンションだった。それぞれ6×6の窓があって、それらは閉ざされていた。各階の窓を開けていき、最上階を開けられればその縦列に対応するレジスチルの種族値が上がるらしかった。僕は「『すばやさ』の1をお願いします」と言った。すると、一番右端の1階の窓が開いた。そこには「ワァ…ァ」と涙を流すナガノ先生の描く芋のキャラクターがいた。僕はとたんに、何倍もの重力に襲われたように地面に叩きつけられた。そして叫んだ。ナガノの描写する、戯画化された世界の影に隠れた圧倒的なリアリズムに叩きのめされたのだ。何千、何万もの言語化不可能な感情が僕の胸を押し潰し、僕は起き上がれなくなる。タモリは半分諦念、半分軽蔑の目で僕を見下ろす。「こういうことなんですよ」最上階の窓を開ければ、ナガノの漫画が完成する。してしまう。たった1コマでこの重み……漫画が完成した時、僕の身体は原型を保っていられるのか? 僕は涎を垂らしみっともない呼吸で生を繋ぎながら、タモリを睨む。あなたはなんて残酷なことをしてきたんだ。レジスチルの種族値は、現時点でも十分と言えるほど高い。この数値まで持ってくるのに、この人はいったい何作品のナガノ漫画を……。それは想像するだに胸が引き裂かれる真実だった。タモリは「君のような感性の高い若者が現れるのを、待っていたのですがね。やっぱり君も他の奴らと同じでしたか」消えゆく意識の中、僕は血涙を地面に落とす。それは生理反応か、ナガノによって粉微塵にされた感情の一片のなけなしの抵抗なのか、わからなかった。僕は意識を失った。
という夢を見て起きた。時計を見ると16時だった。
16時!?
一瞬パニックになったが、まあいいやと諦めた。海外旅行に来ておいて16時から行動開始したなんて言ったら、人によっては怒られそうだ。でも仕方ない。起きたら16時だったんだから。しかしおかげさまで、扁桃腺の痛みは治まっていた。これだけの睡眠が必要だったのかもしれない。
服を着替え、「MAID SERVICE PLEASE」の札をドアノブにかけて、宿からバス停へ向かった。今日もまたサンフランシスコに行くところから旅行が始まる。

電車でサンフランシスコ・キングストリート駅に到着後、昨日歩いたのとは反対方向に歩いてみた。何があるのか調べながら、なんとなく目的地を決めた。
あったのは、大量のガラス片だった。

絵に描いたような高架下だった。とにかく地面にガラスが散らばっていて、治安がいいとは言えない感じがした。駅の真裏が荒んでいるのは、京都駅っぽい。ここはまた別の事情があるのだろうけど。そこらじゅうの壁にグラフィティが刻まれていて、やっぱヒップホップは高架下で産声をあげるんだな、と思った。

ここめっちゃガラス多いな〜と思ったら、しっかり窓が割れていた。埃とは違って、ガラス片は自然発生するわけではない。地面を覆いつくす無数のトゲトゲすべてに因果が内蔵されていると思うと、不思議な気持ちになる。

「Broken Glassが全方位にあるから注意せよ」みたいな貼り紙があった。靴の中にガラス片が入ってきて、痛かった。
街の治安というのは通り単位で決まっていることが多いので、ミッションストリートという安全そうな名前の通りまで各ストリートを垂直に横切って移動した。さらに進み、近くにミッション・ドローレス・パークという自然公園を見つけた。そこで休憩することにした。本当は今日は、ゴールデンゲート・パークという世界最大の造成された自然公園に行きたかった。そこはなんと、日比谷公園の25倍もの広さがあるらしかった。でも今日は人との待ち合わせがあったから、スケジュール的にカットせざるを得なかった。寝坊したせいだ。悲しいけど、ドローレス・パークで妥協した。ここは、日比谷公園の1倍くらいの広さだった。

ドローレス・パークではコヨーテ・アラートが発令中だった。気を引き締めた。結局サンフランシスコでコヨーテに出会うことはなかったが、リスは見かけた。アメリカはリスがとにかく多いらしい。
ドローレス・パークの草原に寝そべり、待ち合わせの相手を待った。彼は、ぜんぜん来なかった。後で聞いた話によると、スタンフォード大学から出発した彼は、乗るべきシャトルバスを間違えたらしく、とんでもない場所に来てしまっていた。

しっかり、カリフォルニア規模で間違えている。落ち合うにはまだ時間がかかりそうだった。
このまま公園で待っていると、凍え死にしそうだった。サンフランシスコの夜は、夏でも寒いのだ。一人行動を再開した。

ミッション街を超えた丘の上にある、カストロ地区に来た。ここは、世界でも指折りの規模のLGBTQコミュニティの街だ。カストロ地区は、アメリカではじめてゲイを公表しながら選挙に当選した市会議員であるハーヴェイ・ミルクが活動の拠点とした場所だった。好きな映画監督ガス・ヴァン・サントの『ミルク』を通して僕は彼の人生を知って、それからずっと来てみたいと思っていた。横断歩道もレインボーフラッグの色になっていた。
GLBTミュージアムという歴史資料館が一番の目当てだったけど、閉館時間を過ぎていて、入れなかった。仕方ないので、そぞろ歩いた。さすがのゲイタウンらしく、肌面積の多い黒いタンクトップを着たマッチョな人が道の真ん中で(他人と)キスをしていた。

ハンドジョブ・ネイルズ&スパ。

このKNOBSは「The gayest(もっともゲイ)」な店と言われているらしい。大量のドラァググッズや性具が売られていた。
他にもLGBTQ関連の書籍をまとめた書店なども入った。見れそうなところは、あらかた見た。クラブとかには入る勇気も金もなかったので、やることがなくなって途方に暮れてしまった。
待ち合わせの人は、さらに遅れそうだった。目的のバスがなぜか運行していなかったり、ついにはGoogleマップが嘘をつき始めたりと、踏んだり蹴ったりの目に遭っているみたいだった。かわいそうに……。自分も旅行してわかったが、外国の交通の利用はなかなか難しい。定刻遅れが多いのは定番だが、バスなどは定刻よりも早く来て先に行っちゃったりするのだ。バス停にはバス停の名前が書いてないし、カルトレインという電車は案内表示板がバグっていて、嘘の現在地を伝えてきたし、BARTという列車の案内表示板は、進行方向を示す矢印が実際の進行方向の真逆を向いていたし……。
向こうは相当大変そうだったが、自分の方も限界が近かった。指先が凍りついて、スマホが打てなくなってきた。反省した。もっと防寒に気を配るべきだった。日本の暑さにかまけて、まさか夏に凍えることはないだろうと思っていた。地中海性気候の夜、寒すぎる。
僕はドローレス・パークに戻り、中央の坂を往復ダッシュした。サンフランシスコに来てわかったことは、ここには変な人が多すぎて、ちょっとしたことじゃ驚かれないということだ。わかりやすく変な人も多いけれど、もっと国民性には至らない細かなレベルで……たとえば、中央分離帯であぐらをかいて信号を待つとか、工事中の作業員に対して気軽に雑談をしかけるとか、通話が盛り上がったあまりに手に持っていたハンバーガーをゴミ箱の上に置いちゃうとか……そういう細かい動きが、東京では意外に見かけないものなのだ。東京の人間はこんなにもたくさんのことを「やっていない」のか、と思わされた。
だから、暖を取るために坂を往復ダッシュする程度なら、怪訝な目で見られることは無いだろう。すでに横でやっている人いたし。その人は、プードルをかごに載せて輝く小型自転車を押しながらダッシュしていた。僕も追いかけるように走った。疲れるまで。

疲れた。寝そべった。身体は少しだけ温かくなった。運動のカードは使ったので、あとは日記を書いたり、公園の環境音を収録したりして、時間を潰した。
すぐにまた身体が冷気を吸い込んで、震えてきた。もう、あまり考えないことにした。
待ち合わせの人と、ようやく合流することができた。お互い憔悴しきっていて、正常な判断ができなくなっていた。時刻は20時を過ぎていた。帰りの時間や食事のことを考えると、市街地から離れたこんな場所で落ち合ったところで、もうどこにも行けないように思えた。僕は、「今からサンフランシスコで一番高いところに行こう」と提案した。
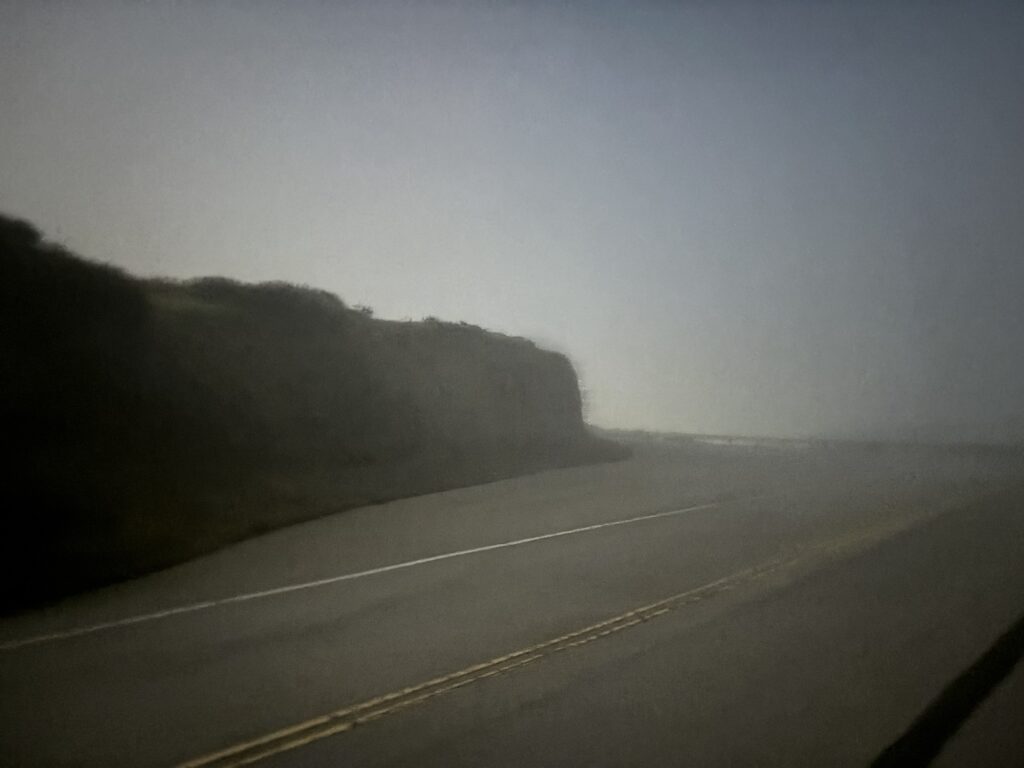
Uberを拾って、ツインピークスという丘のふもとまで来た。ここからは車は通行できなかった。霧に囲まれて、何も見えなかった。

月明かりと、頂上の燃えるような謎の赤い光だけが頼りだった。風が吹きつけた。登れば登るほど、寒さは厳しくなった。この道がいつ終わるのか、わからなかった。これ以上進んで、はたして帰れるのかとかは考えなかった。僕たちは、ここで死ぬのかと思った。この世ならざる体験だった。

頂上が見えてきた。

赤い光は、格子に囲まれた謎の人工施設が発していた。『FireWatch』みたいだ。霧も濃く看板がうまく読めなくて、結局何の施設なのかはわからなかった。おそらく電波塔……?

振り返ると、サンフランシスコの夜景があった。写真だと霧でぼやけているが、肉眼でも同じくらいぼやけていた。僕は胸がいっぱいになった。晴れているよりも、よっぽど美しかった。心から、この場所に来れてよかったと思った。冷気は着々と身体を蝕んでいるので、この景色をいつまでも見つめつづけることはできなかった。戻らねば。
そのあと、Uberに乗って真顔で地上に戻った。
帰りの電車もなんとか間に合った。
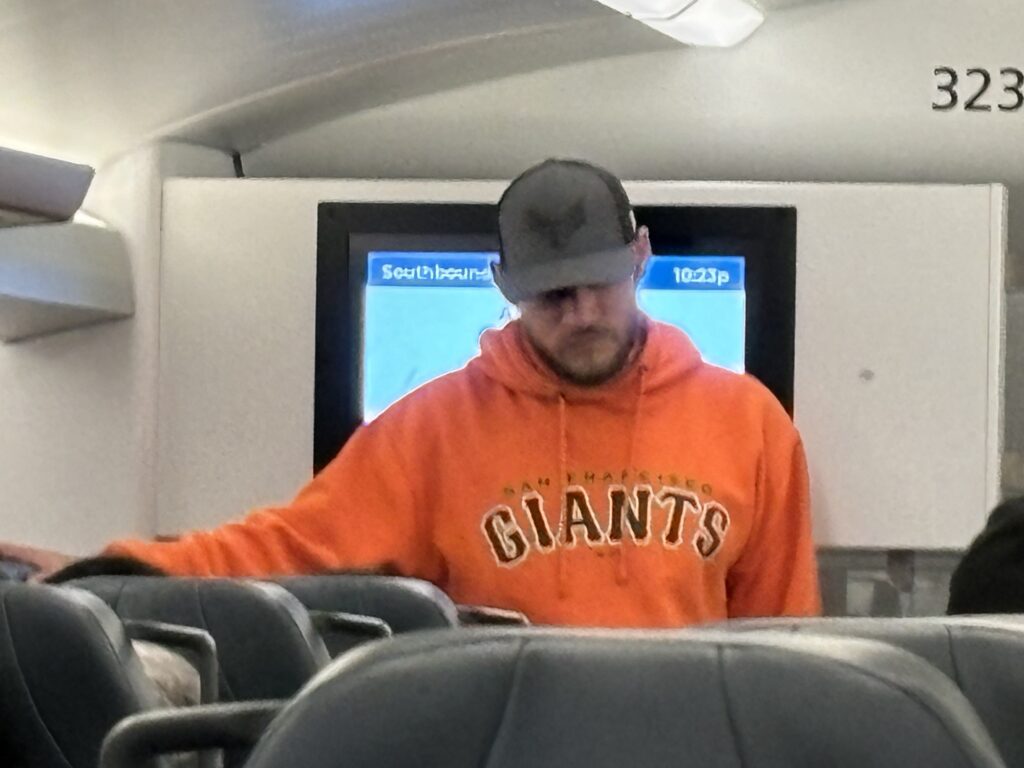
電車内では、この男が何故かずっと車内案内表示の目の前に立っていたせいで、いま何駅にいるのかずっとわからなかった。
宿に戻ると、今日も「MAID SERVICE PLEASE」の札が地面にはたき落とされていた。清掃もされていなかった。どうして。怒ってるの?
ベッドに身体を投げおろした。今日もすごく楽しかった。海外旅行では、交通や気候になじみがなく、言葉や常識が異なることもあり、様々なよくわからなさに包まれる。違和感もディスコミュニケーションも、すっきりとした答えを得られないまま、まあこうして今日も生きて宿に戻れているのだからいいかと自分を納得させる。道程を思い返すと、すべてが奇跡の連続のような気がしてくる。今日は一体いくつのサイコロを振ったんだろうと思いながら、眠りに落ちる。。。
